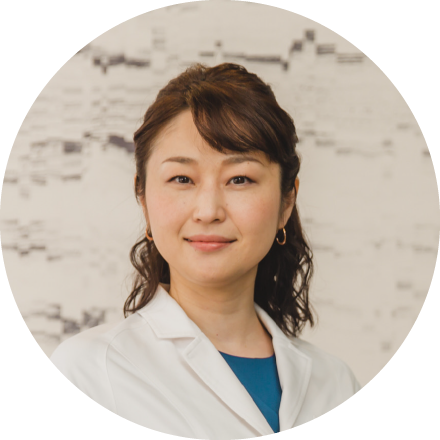
工藤紀子
小児科専門医・医学博士



今回のテーマは「カルシウム」です。前回ご紹介したビタミンDと一緒に摂ることで、強い骨や歯を作る大切な栄養素です。
カルシウムは体内にたくわえられており、その約99%が骨と歯に存在します。
残りの約1%は血液中に溶け込んでいますが、この血液中の1%がとても重要な役割を果たしているのを知っていますか?筋肉や心臓の収縮、脳での情報伝達など、生命活動に欠かせない働きをしています。また、「カルシウム不足になるとイライラする」と言われるのは、神経の安定にもカルシウムが関与しているからです。まさに、生きていくために欠かせない栄養素といえるでしょう。
カルシウムが不足すると、体に異変が起こります。体は血液中のカルシウム濃度を一定に保つために、骨や歯に蓄えられているカルシウムを溶かして血液に供給します。その結果、骨や歯がスカスカでもろくなり、特に高齢者は骨粗鬆症のリスクが高くなります。
また、溶けだしたカルシウムが血管に蓄積することで、動脈硬化を引き起こす可能性もあります。カルシウムを適切に摂取することは、健康な生活を送るためにとても重要です。

これまでお話した通り、骨や歯からカルシウムが溶け出すのを防ぐためには血液中に十分なカルシウムを保つことが大切です。しかし、東京大学の調査によると、日本人の男女すべての年齢層でカルシウムの摂取量が不足しているという結果が出ています。長年にわたり「カルシウムは大事」と啓発されてきたにもかかわらず、この状況は改善されていません。
その背景には、以下のような理由が考えられます:
特に12~14歳の思春期の子どもたちは、カルシウム不足が深刻です。この時期は骨量が増加する大事な時期ですが、学校給食がなくなることで牛乳を飲む機会が減り、摂取量が足りなくなってしまいます。一方で、小学生の子どもたちは学校給食で牛乳を飲むため、完全に足りているわけではありませんが、ある程度のカルシウムは摂取できています。

カルシウム不足を補うために、牛乳1杯を毎日飲む習慣を取り入れていきましょう。牛乳1杯(200ml)には約220mgのカルシウムが含まれています。年齢や生活習慣にもよりますが、推奨量と実際の摂取量の差はおよそ牛乳1杯分程度。この1杯で不足を解消することができます。
脂質が気になる方は、低脂肪牛乳や無脂肪牛乳を選んでもOKです。これらでもカルシウム量は変わりません。また、牛乳独特のにおいが苦手な方にも、低脂肪や無脂肪タイプならさらっと飲みやすいのでおすすめです。
毎日の小さな習慣が、未来の健康な骨や歯を作ります。

カルシウムは、牛乳、ヨーグルト、チーズなどの乳製品や、骨ごと食べられる魚類、大豆製品に多く含まれています。先ほど「牛乳1杯を毎日飲む」ことをおすすめしましたが、続けるのが難しい方もいるかもしれません。
栄養に関して私が大切だと思っているのは、「長く続けられること」。そこでおすすめしたいのが、みそ汁に牛乳をプラスする方法です。
牛乳を加えることで、みそ汁にコクやうまみがプラスされます。さらに、味を濃くしようと味噌を多めに入れると塩分過多になりがちですが、牛乳を足せば自然と減塩効果も期待できます。最初は少量から試して、慣れてきたら少しずつ増やしてご家庭でちょうど良い量を探してみてください。

もし牛乳が飲めない場合は、豆乳でもOKです。豆乳にもカルシウムが含まれていますが、吸収率は牛乳の方が高いことを覚えておきましょう。

みそ汁の具材も工夫すると、より効果的に栄養を摂取できます。

みそ汁以外のスープに牛乳を加えるのも良い方法です。自分に合った方法で、無理なくカルシウムを摂り続けることが大切です。毎日の食事に少しの工夫を取り入れて、家族みんなで健康を維持しましょう!
次回は新学期・新生活が始まる時季に増える便秘についてご紹介しますのでお楽しみに!
私のモットーは「楽に、楽しく、安全に」。これからも日常生活に取り入れやすい情報をお届けしていきますね。
カルシウムの食事摂取基準(mg/日)
性別
男性
女性
年齢等
推定
平均
必要量
推奨量
目安量
耐用
上限量
推定
平均
必要量
推奨量
目安量
耐用
上限量
0~5
(月)
ー
ー
200
ー
ー
ー
200
ー
6~11
(月)
ー
ー
250
ー
ー
ー
250
ー
1~2
(歳)
350
450
ー
ー
350
400
ー
ー
3~5
(歳)
500
600
ー
ー
450
550
ー
ー
6~7
(歳)
500
600
ー
ー
450
550
ー
ー
8~9
(歳)
550
650
ー
ー
600
750
ー
ー
10~11
(歳)
600
700
ー
ー
600
750
ー
ー
12~14
(歳)
850
1,000
ー
ー
700
800
ー
ー
15~17
(歳)
650
800
ー
ー
550
650
ー
ー
18~29
(歳)
650
800
ー
2,500
550
650
ー
2,500
30~49
(歳)
650
750
ー
2,500
550
650
ー
2,500
50~64
(歳)
600
750
ー
2,500
550
650
ー
2,500
65~74
(歳)
600
750
ー
2,500
550
650
ー
2,500
75以上
(歳)
600
750
ー
2,500
500
600
ー
2,500
妊婦
(付加量)
+0
+0
ー
ー
授乳婦
(付加量)
+0
+0
ー
ー
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」より
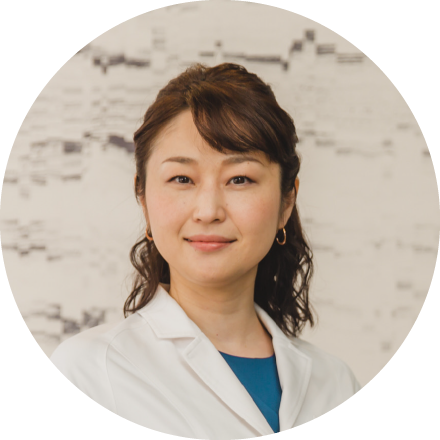
工藤紀子
小児科専門医・医学博士
プロフィール
順天堂大学医学部卒業、同大学大学院小児科思春期科博士課程修了。栄養と子どもの発達に関連する研究で博士号を取得。日本小児科学会認定小児科専門医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/保育園、幼稚園、小中学校の嘱託医を務める/現在2児の母。クリニックにて、年間のべ1万人の子どもを診察しながら子育て中の家族に向けて育児のアドバイスを行っている。