発酵人
映画研究者 三浦哲哉さんが語る
感動が面倒を超える自炊のすすめ
2024/05/16
発酵人
2024/05/16


映画研究を専門とし、『サスペンス映画史』『映画とは何か フランス映画思想史』などの著書のある三浦哲哉(みうらてつや)さん。食には幼い頃から関心があり、食べることが好きだったといいます。「映画と食には共通点がある」という三浦さんに、映画と食や、自炊についてお話しいただきました。
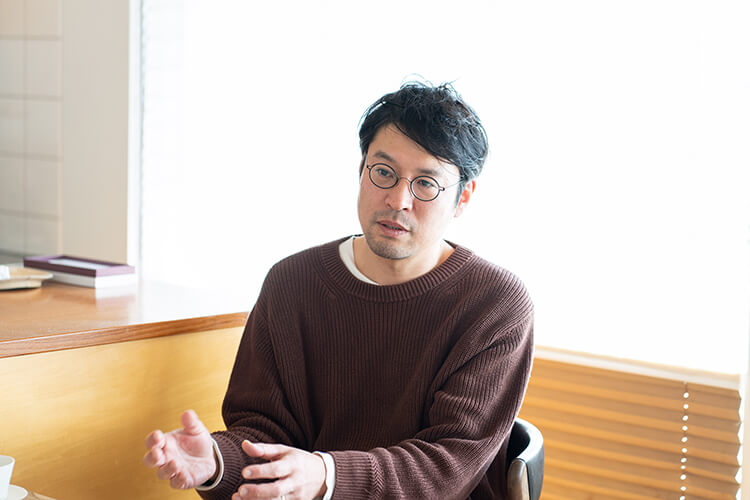
「映画というのは、日常の外に広がる別の世界をスクリーンという窓を通して知る、疑似体験するものです。食の楽しみも映画と通じるところがとても多いと思っています」と語る三浦哲哉さん。
幼い頃から、 “いろいろなものを食べたい”という欲求が強くあった三浦さんは、いつか東京や海外に行って食べてみたいと、口にしたことのない料理に憧れを募らせていたそうです。
「でも、上京した後も、研究者を目指していた若い頃は、なかなか素敵なレストランに行くことができませんでした。そこで、レシピ本や料理エッセイを読んでは、食べたことのないさまざまな料理をつくるようになったんです。当時の僕の日常は、自由といっても限られていました。お金がないとか、旅ができないとか、好きな仕事にまだつけそうもないとか。だからこそ、映画を観れば救われる思いがしたし、料理をすれば息抜き以上の楽しみ、喜びを感じることができました。映画も、自炊も、僕にとっては日常から外へと窓を開いてくれるものだったのだと思います」

そんな三浦さんの食に関する最初の著書になったのが、世の中にある料理本や料理エッセイを批評した『食べたくなる本』です。福島県出身の三浦さんが東日本大震災を経て思考した「食とはなにか?」も大きなテーマとなっていました。
「僕の映画研究の題材のひとつに、サスペンスがあります。サスペンスとは、日常が何か別の形になってしまったり、自分の足場がぐらついたりする出来事を描いたもの。これまで意識することのなかったふつうの日常をあらためて意識させてくれる面もあります。震災と原発事故は、自分にとってふだんの食をあらためて見直すきっかけになる出来事でした。ふだん食べていたものについて自分が知らないことばかりだということを強く意識しました。
それで当時、福島県でドキュメンタリー映画を上映し、地元のみなさんも交えてディスカッションをするイベントを開いたりもしました。そこで米農家さんと出会い、震災後にもう一度米づくりを再開する中で直面したご苦労などについて、つぶさに聞かせていただくこともできました。これらのことが、あらためて食について考え直す機会になり、『食べたくなる本』を書く動機になったのです」

三浦さんの最新著書『自炊者になるための26週』は、1週に1章ずつ、課題をクリアしていけば、26週つまり半年で、誰でもすすんで自炊する“自炊者”になれることをコンセプトにした本です。
そう聞くとレシピ本かと思いますが、実はそれだけではありません。三浦さんが考える、自炊をする際のアプローチの仕方や面白がり方を、ときに具体的に、ときに文学的な語り口で、またときには科学的、哲学的な視点を介して伝えています。
そのなかで、自炊を続ける大切な要素のひとつに、「風味(主ににおい)」に誘われ、その喜びを能動的に味わうことがあると語る三浦さん。
「おいしさにはざっくり2系統あると考えています。ひとつは、舌で感じられる、違和感のない落ち着く味です。これを“コンフォタブルな感覚”という意味でC感覚と名付けました。アメリカでは「コンフォート・フード」と言いますが、万人を喜ばせようとして設計された既製品の味をイメージしていただければわかりやすいと思います。もうひとつは、主に鼻で感じられる感覚で、日常の外から届いたにおいによって、新たな発見があったり、ゾクゾクするような感覚を覚える、“フレイバーを感じる感覚”、F感覚としました。野菜や魚といった素材が持つ個性とそのゆらぎ、季節ごとの変化を楽しめるのも、鼻という器官が感知するフレイバーゆえです。風邪をひくと食べ物の味の違いがわからなくなることがあります。これは鼻が詰まって、フレイバーが感じられなくなるからです。
通常これらの感覚は混じり合っています。でも実はそれぞれ別々に鼻と舌に与えられているため、それらを2系統として取り出してみようと考えたのです」

C感覚とF感覚について考えるきっかけに、三浦さんのお父様とお母様のやりとりがあったそうです。
「かつてうちの父は、母がつくったおでんより、コンビニエンスストアで買ったおでんのほうがおいしいって言っていたんですね。たしかに母のおでんはコンビニのおでんに比べるとわかりやすいうまみに乏しい。でも、一から出汁をひき、野菜そのものの風味がありました。いまにして思えば、父の言う「おいしい」と母の言う「おいしい」は別物だったんです。こういう混乱を解きほぐすためにも、C感覚とF感覚、というような言語化を試みた次第なんです」
コンビニのおでんのように多くの人にとって馴染みがある安定した味わいはC感覚を、材料などによっても風味が変化する家庭でつくるおでんの味はF感覚を刺激します。
「僕は、C感覚を充たすコンフォートな味の商品も便利だし、否定するつもりはありません。でも、母のように自炊で何かをつくるなら、F感覚を重視したい、それがこの本の主張のひとつです。家のおでんは家の味。母が好む風味を集めてつくった、取り替えのきかないオンリーワンの味です。うまみを足しすぎていないから、近隣の畑で採れた大根などの風味もそのまま残っています。そうしたF感覚を楽しめたらと思うんです」

近年は、味が手軽に決まりやすいことを謳った、C感覚にフォーカスした料理本も人気があります。しかし、C感覚一辺倒ではなく、時にF感覚を楽しむことこそ、自炊者にとって大切だと三浦さんは考えています。
「料理に自信が持てないという人のなかには、100点の味、正解の味がどこかにあるはずだと想定して、自分のつくった料理は、90点?それとも75点?というように減点法で考える発想に陥ってしまっている人もいるのではないでしょうか。これで味が決まっただろうかと不安になったり、まとまっているだろうかと考えたり。でも、自炊では味が決まらなくても、まとまっていなくてもいいと僕は思うんです。今日手に入れた食材があって、それが例えば、ゴボウでもイワシでもいいんですが、そこには何かしら個性的な風味があります。その風味をシンプルに楽しもうとするなら、加点しかないですよね。調理や加工は最小限でよくて、あとはゴボウならではのいい香りを楽しむ。イワシの香りを楽しむ。バラつきも個性としておもしろがる。あぁ、今日の一皿はこうなったなと、そのことをF感覚で、能動的に楽しみたい。それだってもちろん毎日でなくてよくて、すべてC感覚に染まりきってしまわないように、F感覚を大切にしたいと思っています」

そうは言っても、自炊は手間がかかるし…と考える人もいるかもしれません。そんな人のために、三浦さんは、感動が面倒を超えるためのアプローチを、さまざまな角度から伝えています。
「たとえば、揚げ物を楽しむなら、『まずバットを3つ用意する』などは、シンプルですが、面倒だと感じがちな揚げ物をスムーズに調理するコツのひとつです」
また、信頼のおける八百屋さんや魚屋さんを見つけて先生にする、よりおいしくなる器を用意する、可能なかぎりフェアに家事分担するなど、自炊を面倒に思わず、感動につなげる方法は、さまざまあると三浦さん。
「面倒なことを、人は無意識に遠ざけようとします。ですから、そうしないためにデザインする、一言で言えば、習慣形成をしっかりとすることも、自炊を続ける秘訣になります。面倒だと感じる割合をぐっと下げる、そのためのポイントを見つけて、自炊が面倒に感じないよう橋渡しをするのがこの本の役割だと思っています」

同書籍には、発酵食品についての記述もあります。三浦さんは発酵食品をどのように捉えているのでしょうか。
「たとえば、味噌は自分の帰る場所という感じがしますし、発酵食品は味覚のベースになるものだと思っています」
小さいときから、出汁や醤油、味噌の味に馴染みのある日本人。そうしたにおいをかいだり、味わったりすることは、日本で生まれ育った人にとっては、初期設定のようなものだと三浦さん。
「もし、出汁や醤油を楽しむベースのようなものを持ち合わせていないと、和食を楽しむことは難しいですよね。発酵食品は、日本人には当たり前のものであっても、馴染みのない海外の人にとっては、最初は風味が強すぎる、臭くて仕方がない、と感じたりすると思うんです。それが、馴染んでくるとだんだんと芳醇な香りだと感じることができるようになるんですよね」
また、ときに発酵食品は“ノイズキャンセリング”の役割を担うといいます。
「土のにおいが強いごぼうや、刺し身などは、慣れていない人にとっては違和感が強く感じられるかもしれない食材です。海外の人のなかには鼻先に突きつけられたら、びっくりしてしまう人もいるのではないでしょうか。こうした風味の強い食材が、醤油や味噌、酢、酒といった発酵食品と一緒になると、たちまちクセとクセが互いを打ち消しあいます。つまりノイズキャンセリングして、風味の好ましい部分だけがくっきり際立ちます。自然に近いものを過度に加工することなく受け入れやすくしてくれるのは、発酵食品の役割、魅力のひとつではないかと思います」

発酵食品を手づくりする家に育った三浦さんにとって発酵のにおいは懐かしく、うれしいものだといいます。また、そうでない人にとっても自分でつくればいつからでも発酵食品を楽しむことができるし、身近に感じられると考えています。
「実は、うちの娘は最初『甘酒は臭いから嫌だ』って言ったんですよね。それに僕はショックを受けてしまって。でも、考えれば当然なんですよね。それまで経験がないわけですから。そこで、自宅で甘酒をつくってみることにしました。家でつくれば過程を見ることができるし、そうすると安心感もあいまって、とてもおいしく感じられますよね。
乳酸発酵と麹菌を用いたかぶら寿司も自分でつくっているんです。富山県で初めて食べたかぶら寿司に感動したのがきっかけでした。自分の見知らぬ土地の発酵食品に最初は違和感を覚えることもあるだろうと思います。その土地ならではの風味に、他人のプライベート空間に入り込むときのような抵抗感を覚える側面も。でも、これまで出会ったことのなかった味に近づいてハードルを超えることは、素晴らしい喜びとスリリングな体験になりますね」
かぶら寿司を手づくりするのは、難しそう…という反応も多いそう。しかし、現代だからこそできると、三浦さんは感じています。
「かつて、かぶら寿司は、雑菌などが繁殖しない雪深い冬があり、脂ののった氷見ぶりが捕れた富山県や石川県だからこそできた郷土料理です。でも、今は県外からいくらでも氷見ぶりを購入できますし、真空パックや発酵温度をキープできる機器を利用すれば素人でも失敗なくつくることができます。」
文明の利器こそ発酵の味方と、笑顔の三浦さん。難しそう…、ハードルが高いのでは?と思わずに一度試してもらえたら、意外と簡単にできますよと、教えてくれました。

最後に、どんな人にこの本を届けたいですか?と聞いてみました。
「これから一人暮らしを始めるという人にも入門書として読んでいただきたいですが、すでに料理はできるけれどまだあまり楽しめていない、もっと楽しみたいという方にもぜひ参考にしていただきたいです。◯◯は裏切らない、という言い方がありますよね。たとえば語学であるとか筋トレであるとか、自分のペースで続けることができて、やればやるだけリターンがあって、幸福感が得られるもの。自炊もまさにこれです。たとえ、お金がなくてもおいしいものは自分でつくれるし、たとえ好きな仕事に就けなくても出世が遅くても、自炊して幸福になってしまえばよいではないですか、と思います。20代の僕にとっても自炊が心の支えでした。今の妻とお付き合いしていたとき、同世代の金銭的余裕のある連中のようにレストランには行けませんでしたが、家でおいしいものをつくることができたと思いますし、それで心の平静が保てました。もちろん、レストランにはレストランの魅力があります。でも自炊には自炊の素晴らしい喜びがある。ぜひ、一章ごとに積み重ね、一つひとつ峠を超えて自炊者になってもらえたら、とてもうれしく思います」

1976年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コース博士課程修了。青山学院大学文学部比較芸術学科教授。専門は映画研究。食についての執筆も行う。著書に『LAフード・ダイアリー』(講談社、2021年)、『食べたくなる本』(みすず書房、2019年)、『『ハッピーアワー』論』(羽鳥書店、2018年)、『映画とは何か──フランス映画思想史』(筑摩選書、2014年)、『サスペンス映画史』(みすず書房、2012年)。近著に『自炊者になるための26週』(朝日出版社、2023年)がある。